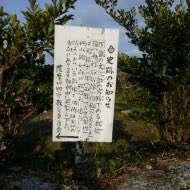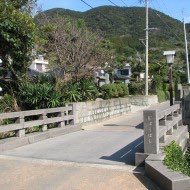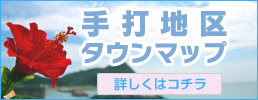甑島航路
高速船甑島(長浜港~里港~川内港)
結Lineこしき(長浜港~里港~串木野新港)※船名のLineは筆記体
現在、上記の2隻が就航中です。
“御竜朝墓(おたつちょうばか)”
寛文12年(西暦1672年)、甑島地頭第5代、比志島監物灰所と記録された自然石(花崗岩)の碑が、手打字薗山部落の海岸近く(往時は芦草の生えた砂丘)に建っている。第5代地頭比志島監物の地頭年譜は、慶安元年から寛文7年まで20年と記録されているので、監物没後その遺徳を頌して建立されたものと伝えられる。(下甑村郷土誌より)




“常楽寺墓地”手打小学校の裏側に位置する。
常楽寺の寺社屋敷帖に拠る面積は5畝4歩、寺跡の背後につづく丘陵地である。墓地内に石棺の所在する墓所があり、地頭、常楽寺住持、手打部落各郷士の石碑が建っている。石碑は何れも寛文(西暦1660年)以前のものは風化度著しく、銘が消滅した古い石碑等が多い。
(下甑村郷土誌)より抜粋



1974年10月6日から20日まで、この地において、川内青年会議所と下甑村の協力で日本で始めての実験コースとして開催されたところであり、記念碑が建立されています。記念碑建立の場所は、手打地区の佐之浦海岸近くです。
OBSとは、
財団法人日本アウトワード・バウンド協会(OBS)は、「社会の中で『自己表現』出来る人を育てる」「教室では学べない、『生きる力』を育む」ことを目指して活動している、非営利の世界的冒険教育(野外体験教育)機関です。大自然でのダイナミックなチャレンジを通して、「本気」で人と関わることで、自分の可能性に気づき、人を思いやる気持ちを育むプログラムを、子どもから大人まで、性別や体力、経験を問わず多くの人に提供しています。
冒険教育活動の拠点となるOBS校は、長野県の最北端の小谷村というところにあります。


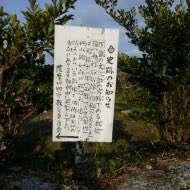
丹山様(たんざんさま)
手打、字釈迦元にある仏像(石仏)を丹山様、あるいは釈迦堂様という。
元禄11年(1698年)補陀山常楽寺第10代住僧、丹山観和尚が、仏道布教のため、この地に釈迦巡錫の石像を建立した。
部落民は、これを機縁に熱心な信徒があらわれ、供養塔(五輪ノ塔)等を奉寄進し、釈迦講を営んで厚く信仰したという。
下甑村郷土史より抜粋



“甑島地頭仮屋跡”
現在の薩摩川内市下甑支所の所在地が旧甑島地頭仮屋跡である。
地頭政治
甑島は、古来異国船の漂着あるいは来舶地であったことと、長崎来航の支那、オランダ船の航路に接近していることなどで、警備の必要もあることから、甑島地頭に任じ政治を行わしめた。
下甑郷土誌より


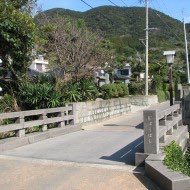
“大照寺”沿革
真宗大谷派の寺である。明治23年3月17日に、独立の説教場開設の請願書を提出、同年5月21日開設許可がおり、明治24年9月21日御本尊並びに両聖人御影下附、更に明治33年3月7日には木仏本尊を奉安した。昭和27年9月2日に大照寺を公称、同年12月9日登記完了した。
主な建築年度
本堂・明治23年建築60坪
庫裡・大正2年建築40坪1,100円
敷地・452坪
場所は、下甑郷土館の隣です。現在の住職は加来賢隆師です。



津口番所跡(手打の歴史)
江戸時代において、海上取締り、或いは監視のため、陸路境目、海路、津口の展望のきく岡の上などに番所を置いて厳重に監査したものである。
津口番所は主要な港、津口に置いて厳重な取締りを行った。
下甑では、津口番所、異国船番所として手打(津口)に置かれていた。
この施設は、当時、宝永年間(西暦1705頃)にこの地にあったものをイメージ的に復元したものである。
手打漁港の中央付近、県道沿いに復元建立されている。



「大東和戦争戦没者之碑」(鹿児島県知事寺園勝志書)は、昭和34年(1959)12月1日招魂碑の隣に建立された。碑文は次のとおりである。
(碑文)
「大東和戦争に於いて護国の華と散りし郷土の勇士158柱の御霊は産土の神の御前に近く今や神鎮まりませり我ら茲に謹みて哀悼の誠を捧げ忠魂を久遠に偲び冥福を永世に祈り奉らむ」
昭和34年12月1日 大東和戦争戦没者慰霊塔建立期成同盟会
小さな村の小さな集落からも先の大戦に参戦し、国家のためと信じ捧げた158人の尊い命我ら決して忘れてはなりません。手打地区では、毎年10月に区民に呼びかけ戦没者追悼法要を行っています。
「招魂碑」は明治39年4月16日建立された。日露役・十年役の戦没者が奉られている。



法雲寺
手打地区港集落の旧道に接して位置する。浄土真宗本願寺派の寺院である。明治42年(1909)に寺院創立公許を得て、同44年(1911)3月8日、本堂の上棟式が行われた。
歴代住職初代(開基)は、八渕蟠龍師であり、現在は4代目井芹大心師である。
平成16年3月2日~4日には、「即如門主甑島組ご巡教」が行われた。
この行事には、本願寺第24代大谷光真門主をはじめ随員10名、甑全島内から本願寺派の寺院6か寺から120名が集い、手打の法雲寺で盛大に実施された。
法雲寺は、手打地内にある貴重な歴史的建造物でもある。